私たちは、「学習する時になかなか覚えられない」「スポーツで練習通りに試合で成果がでない」「大事なプレゼンで思ったような結果が得られない」みたいな経験がありますよね。
この著書『習得への情熱チェスから武術』をを読むことによって、一流のスポーツ選手や競技者が実践している最短の習得の考え方や緊張してしまう状況を日常的な習慣にまで落とし込むことによって、私たちでも実践できるようになります。
なぜなら、この著者ジョッシュ・ウェイツキン氏は、チェスと推手と呼ばれる武術の中国武術の世界チャンピョンになった方です。
そんな天才の考えなんて出来るわけない!と思うと思います。
しかし、天才は天才でも努力の天才でした。
私たちとは次元が違うというよりも、私たちがいる努力して進める道の延長線上の先の先の…先にいるような感覚の方でした。
全てを真似しようとは思わなかったです。
しかし、実践しやすいような具体例もあって、これなら、習慣に取り組めるという内容もあったので紹介していきたいと思います。
こんなあなたにオススメ

- 知識を身につけて成果を上げたい
- スポーツや勉強で上手くなるための考え方を知りたい
- 大事な場面で失敗しないようになりたい
要約・書評の記事を読んで得られるメリット

- 効率よく学習するためのマインドを知れる
- 一流の人がどういう思考で学習する対象を見てるかを知ることが出来る
- 大事な場面で失敗しないための準備で必要なことを実践できるヒントが分かる
結論

学習プロセスにおいて必要なことは、3つある
- 恥をかくことを一切気にしない
- マインド増大理論の学習アプローチをとって取る
- ピーク状態でパフォーマンスをできない期間を受け入れること
1恥をかくことを一切気にしないマインド
著書に書かれている考え方で「負の投資」という考え方があります。負の投資とは、とにかくあらゆる失敗から学ぼうとすることです。
私たちは、よく自分の都合の悪いこととかを見てみぬふりをしてしまうことがよくあるじゃないですか?それを、省みないのは学習機会を放棄しているようなものなので、失敗は学べる機会だと考えて、どんどん失敗しましょう。
とは言っても、失敗するのって誰でも怖いじゃないですか?
そんな時に失敗してもストレスを回復させるための方法を知ってれば少しでも挑戦回数が増えるのではないかと思います。
ひすいこうたろう 名言セラピーから失敗から立ち直る、活かす方法
知らないと損する〜行動力を上げる成功者と成功しない人の考え方の違い
本の感想 『SNS夢を叶える』ゆうこす 挫折から乗り越えるマインド
ストレス&リカバリーとは?

ストレスがかかっている状況の時に、ストレスを回復させることで高いパフォーマンス発揮するという考え。
ストレスリカバリー量が多いほどパフォーマンスは高い。
ストレス&リカバリーの具体例
ストレスがかかる緊張状態の時は心拍数が上がっているので、それを下げる訓練をする。例えば、インターバルトレーニングでもも上げを20回やって20秒休みを8セットやる
プロテニス選手が点を決めても、点を決められてもラケットのガットを直すと言うルーティーンでストレスをリカバリしています。
私たちはそんなことをする必要があるのか?って思うかもしれません。
ただ、プレッシャーのかかる大事なプレゼンや重要な会議で結果を出せなかったことありますよね?そんな時に落ち着きを取り戻す、大事な場面に入るまでのルーティンがあると成果が出やすくなります。
2.1落ち着きを取り戻すルーティーン
呼吸。何だそれって思ったかもしれませんが、大丈夫です。吐く息の量を長く、吸うを短くします。(ハースッ ハースッ)というように8秒吐いて、1秒で吸います。逆に吸う時間を長くすると心拍数が上がってしまうので、緊張してしまいます。
2.2大事な場面に入るまでのルーティーン
自分が1番心静かで集中できること前にルーティンを作ります。例えば、自分が1番心静かで集中できることが子供とキャッチボールしてる時だとすると
①フルーツシェイクを作る
②好きな音楽を聴く
③瞑想する
④子供とキャッチボールする
①から③は何でもいいです。自分の気持ちが静まったり、リラックスできることを一番心静かに集中できることにくっつけます。
その後に
①フルーツシェイクを作る
②好きな音楽を聴く
③瞑想する
④大事なプレゼン
とすると、子供とキャッチボールする前のマインドでプレゼンを迎えることができます。
こんなのできないと思うかもしれません。出来なければ自分なりにカスタマイズしていきます。
①朝食を食べる
②好きな音楽を聴く(車で通勤中)
③瞑想する(ただ目を閉じる)
④大事なプレゼン
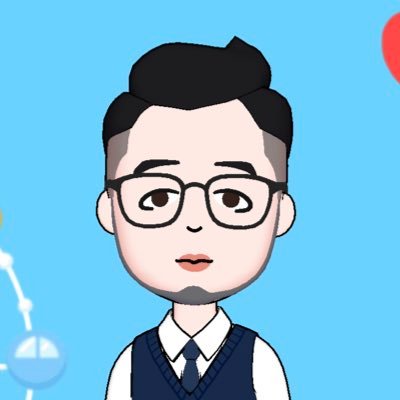
私も子供と遊んでいる時が、一番心が静かで集中できるので、子供と触れ合う前に瞑想を40分する習慣をしようと思います。
2増大理論の学習アプローチをとって取る

競技者の考え方で、実体理論と増大理論というのがあります。
| 考え方 | 成果の捉え方 | 重要視 | |
| 実体理論 | 固定化 | 成果の良し悪しで得意不得意を判断 | 結果 |
| 増大理論 | 流動的 | 成果は努力によるもの | 過程 |
実体理論とは、「自分はこれが得意だ」と固定化された実体であると考える理論です。
結果が良ければ、自分は向いている。悪ければ自分は向いていないと結果に左右される考え方です。
これに対して、増大理論とは成果が「頑張って取り組んだおかげ」と努力の結果によって能力が増えると言うふうに考える理論です。指導される中で、結果よりも過程をフィードバックする傾向が強いです。
プロセスだけを大事にすればいいの?と思うかもしれません。そうではなく、自信を失わない程度に勝ち続けることも大切です。
なぜなら新たな考えを取り入れようするときに、
すべてを捨てて受け入れることが出来ても、独自の才能生かすことを触れることがなくなってしまう。そのことで負け続けてたらそれ自体のモチベーションが下がってしまいます。
例えば、ゴルフのフォームを変えてスコア向上を図っているとします。だけど、スコアは変える前よりも悪くなっています。それは仕方がないです。ただ、低迷している時間が長く続くほど、ゴルフがつまらなくなります。なので、フォームを元に戻して勝つことも必要なのです。
増大理論でいう成長を筆者はこう表現しています。
成長とは往々にして快適や安全を犠牲にすることで促されるもの
習得への情熱 チェスから武術
困難と向き合う心の準備ができていなければならない。結局のところ、泳ぎを覚える唯一の方法は水に入ることしかない。
習得への情熱 チェスから武術
よく、私たちは「私には才能がない。」や「〇〇さんよりも私は〜ができない」と言ってしまいがちですよね。
そういう理由をつけて目の前にある困難やリスクを怖がってしまいます。そんなリスクや困難が来ても立ち向かえる考え方を紹介します。
逆境を利用するとは?
他の人なら避けようとしてしまうリスクも背負い、その瞬間にしか学べないことを最大限利用し、逆境をアドバンテージに変える。障害がきたら学習機会と捉える。
この苦痛の時間に免疫ができるとそのストレス耐性が必ず自分の武器になります。
具体的な逆境と言えるシチュエーションはどんなことがあるか?
また、どうやって対応するか?
結論
→日常的に雑音がある環境で集中が必要な状況を作る。
対応
○気が散っていることをまず受け入れる。
×音から気をそらそうとする
ダメな理由
「シロクマ」の事は考えないようにしてください。
とするとシロクマのことが頭から消えない。
まず音がして、気が散ってしまっているということを受け入れて、その後に別のことに意識を向ける。
例えば、深呼吸を2から3回やってから、タスクを行う。
『反応しない練習』マコなり社長オススメの本を要約・実践してみた
【書評】究極のマインドフルネスをまとめ・要約・感想〜悩みをなくす
3ピーク状態でパフォーマンスをできない期間があるのを知ると痛みが和らぐ
何かを習得しようとする時に、自分が能力が発揮できない期間が必ずあります。それが必ず来るということを知っているだけで、痛みは和らぎます。
例えば、タンスの角に小指をぶつけたら激烈に痛いじゃないですか?それは、不意にぶつけるから痛いのであって、わざと小指をタンスに当てても痛くないですよね。要するに、まずはそういう時間は必ず来るものだと知れば、痛みは減ります。
練習する中で著者は小さな円を描くようにという表現をしています。
どういう意味かというと、1つの技術やアイディアだけを用いて、微細な動きの変化に『なぜここう動くのか?』を説明できます。さらに、それを無意識に動かせるようになることです。
逆に、成長が実感できないからと言って、目先の欲求に負けてしまうことがあります。
例えば、格闘技で後ろ回し蹴りや、飛び蹴りのような派手な技をやろうとしても実際の試合などではなかなか当たりません。
むしろ、地味なジャブとかの方が基本的ですし、そこからの戦略を組み立てたりするのに非常に大事になってきます。
つまり、地味なものを細部まで理解し、無意識にできるようになるまでやることが、遠回りのようで上達の近道であるということです。
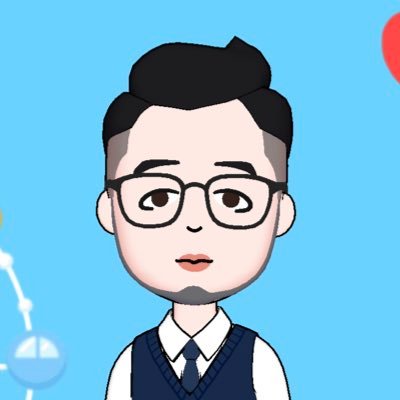
一発逆転のアイディアを考えるよりも地道にコツコツやっていた方がいいということですね。
あとは、ネガティブな感情を抱いている時には、パフォーマンスが下がってしまいます。
例えば、「あの人は絶対許せない」と思っていると、思考がそれに囚われてしまってミスをしてしまう。
そういう時にどうすれば良いかわかっているととても前向きになれると思います。
ネガティブな感情を抱いたときの対処法
例 怒り
①怒りを拒絶したり、遮断したりしようとせず受け入れる。
②それは私のパワーの源であり今燃えている私の内部をさらに熱くさせているガソリンだと思う
※もし、あまり怒りを感じない人は、恐怖心であれば警戒心が高まるなど、ネガティブな感情が来たときにどんな力のパフォーマンスを上げてくれるのかを試すのがいいと思います。
ネガティブな感情の活かし方に興味があるかたはこちらを参考にしてみてください。
【書評】はじめての「アンガーマネジメント」実践ブック・まとめ・要約
習得への情熱 チェスから武術まとめ

- 恥をたくさんかいて失敗から学ぶ
- 結果よりもプロセスを重視する
- 能力を発揮できない時期が必ずあると知る
私たちは、仕事やスポーツで成果を上げたいと思っているけど、私には才能がない、一流の人たちには才能が違うとか思ってしまいますよね。
本書で書かれているマインドは、マッチョな人向けのものなのかもしれません。
ただ、何かを失わないかぎり何かを得ることは出来ません。失敗を一回もしないで、何か成果を上げようとするのは無理な話です。この考え方は今日からでも出来そうと思うものをやっていけばいいです。
もし、習得の情熱 チェスから武術へ に興味を持たれた方は手にとってみてください。



コメント