失敗するのは誰でも嫌ですよね。だけど、失敗したなら何かを学びたい、次に活かしたいと思うことはありませんか?
本書の失敗の科学 著者マシュー・サイドでは失敗から学習する組織代表『航空業界』と学習できない組織代表『医療業界』を対比して、どうすれば失敗から学べるチームを作れるかを書かれています。
決して、航空業界が優れている、医療業界は間違っているという内容ではありません。どちらの業界もたくさんの命を犠牲にしてより安全なシステムが形成されています。
特にアメリカの医療業界では、回避可能な医療事故の被害者が100万人以上、死亡事故が12万人以上という状態でした。
私たちに出来ることは他者の失敗を自分ごととして捉えて、学びにすることではないでしょうか?
- 学習できない組織の特徴
- 失敗から学習するためのマインドセット
- 失敗から学べる組織になるのに必要なこと
学習できない組織の特徴

- 正確なフィードバックがない
- 失敗することは悪いことだと思っている
- ミスをしても自分を正当化する
正確なフィードバックがない
自分たちが行っていることがどれだけ上手くいっているのか?何が失敗の原因か分からないと学習することが出来ません。アメリカの医療業界では、手術中にどのような経緯で亡くなったのかを記録していませんでした。
避けられない事態が起きました。不慮の事故です。と逃げるのが当たり前だったからです。
一方、航空業界では、第三者機関を設けて飛行機事故の原因が何かを徹底的に調べ上げています。そうすることで、2度と同じ事故が起きないための対策を講じることが出来るのです。
現状の把握をするためにも記録をすることは欠かせないのです。
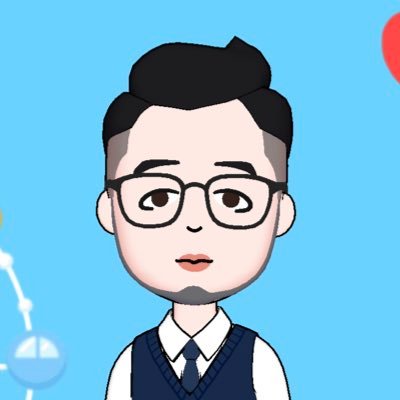
本書では、フィードバックがないのは暗闇でゴルフをするようなものと表現しています。
失敗することは悪いことだと思っている

失敗を100%しないことは不可能です。それは誰もが分かっているのに、なぜ悪いと考えるのかと言うと、非難の対象を決めて問題を終わらせたいと考えています。
失敗を悪いと捉える組織は、どのような行動を取るのでしょうか?
厳罰化
対象者を処罰することによって終わりにしようとしています。問題に対策をすることもないのです。このような組織では
- 上司と部下の信頼関係が築けない
- ミスの報告が減る(ミスが潜在化する)
- 消極的な行動が目立つ
という事態になります。
本書の中で、厳罰するチームとそうでないチームを分けて、ミスの報告と実際のミスの実情を調べました。すると、厳罰するチームは、実際のミスは後者よりも多いにもかかわらず、報告の件数はかなり少なかったのです。つまり、厳罰化は隠蔽を誘発するということです。
とはいえ、ある程度罰をしなければ組織はダラけてしまうと思ってしまうかもしれません。
しかし、本書では放任主義と懲罰は両立すると考えています。そのために必要なのが上司と部下との信頼関係です。
部下に仕事の裁量権を与えると、責任感を持ちます。自分のできる範囲のことを精一杯行なった結果のミスは上司に報告されます。大事なのは上司が人ではなく、システムに目を向けて対策をすることです。
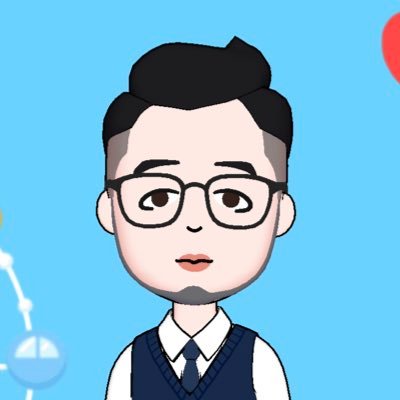
部下の立場であっても、防げた人的なミスなのかシステム的なミスなのかを考えることで無駄に自分を責めなくなります。
知らないと損する悩み事を考えすぎて疲れたとならないようにする方法
世界を単純に考える
脳は直感的に人の性格に原因を求めます。例えば、ある子どもが内向的で人と関わらないのは親が他の子供と関わらせないようにしているからと周りの人たちが考えます。
しかし、実際は人と関わるのも好きだけど、それ以上に絵を描くことに時間をたくさん使っているだけという場合もあります。自分が見えている情報でしか判断しないのです。
本書の中では講釈の誤りと表現しています。講釈の誤りとは、複雑な事象が絡まり合ったことや偶然起きたことを見える2、3つの理由で発生したと勘違いしてしまうことです。
例えば、サッカーの監督が選手に厳しくルールを押し付ける方針だったとします。それで、結果が良ければ選手を厳しく管理しているおかげで勝てたと言うのです。逆にチームが不調の場合には選手の自由な発想力を監督が潰していると非難します。サッカーで勝てるかどうかは監督の采配だけで変わるわけではないです。選手の体調やチームとの相性など複合的な要素を見ても分からないことが多いです。
要するに、何か一つのせいにして考えるのを辞めたくなるような組織は失敗を悪いものと捉えてラクしたいのです。
[要約]悩む力 メンタリストDaiGo クリティカルシンキングを使いこなせ
犯人探しをする
対象者をみつけて終わらせようとしています。自分がそうならないように、ミスを隠すことが増えてるのです。組織としては人よりもシステムの問題に着目しなければ失敗から学ぶ組織は生まれないのです。
ミスをしても自分を正当化する
認知的不協和とは
→自分の信念と起きた事実が違うことに耐えられず、事実を自分の都合のいい解釈をすること
例えば、自分が仕事で連絡ミスしたとします。
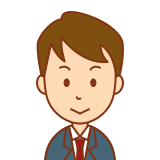
今日の書類は明日の17時までに提出してください。
実際は、明日の9時までに必要な書類でした。
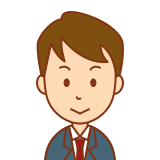
明日までにとしか言われていないのだから、私は悪くない。時間を言わない上司が悪い。
過不足なく上司が言うべきという信念が、確認すればミスは防げたことを見えなくしています。
失敗したことを自分で認めると、自尊心が傷つくので受け入れることが出来ないのです。
失敗を自分で認めるのが難しいのであれば、他人の失敗をたくさん知ることが大事です。その蓄積が自分が失敗するのを防ぐ知識として役立つようになります。
愚者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶ
オットー・ビスマルク
自分の経験からは失敗を受け入れるのが難しいのであれば、歴史を知るのがいいです。
学習するために必要なマインドセット

| マインドセット | 固定マインドセット | 成長マインドセット |
| 考え方 | 能力は生まれながら決まっている | 能力は努力することで伸ばすことが出来る |
| 重視 | 才能 | 努力量 |
| 失敗した時 | 才能がなかったから | 学習の機会(失敗は成長になくてはならない) |
固定マインドセットは、プロセスよりも結果を重視しています。なので、失敗を怖いものと捉えてしまいます。
逆に成長マインドセットは結果よりもプロセスを重視する傾向があります。その中で、確実に自分は成長出来ると思っているので、粘り強く物事に取り組むことが出来ます。
失敗から学ぶ組織の特徴

学習システム(正確なフィードバック)
自分が行っている仕事に対して、正確なフィードバックがないと、エラーを見つけることや改善をすることが出来ません。
具体的な方法としては
- 記録をとる
- 不要な上下関係が発生しないようにする
- 他者の意見を聞く
ミスが起こったとしても個人を攻撃しないで、やり方やシステムに目を向けます。他にやり方がないかを部下や上司とコミュニケーションを取ってベストな選択をします。
自分一人で考えたことだと、バイアスがかかってしまって、間違いを犯すリスクが高くなります。
【書評】知性豊かで創造力がある人になれるLISTENを要約・まとめ
マーシャル・ゲインとは
→大きなことをやるには、小さな改善の積み重ねが大事
大きな目標に対して、小さなステップを周りと共有することがゴールへの近道ということですね。
スタッフの報告(ミスを隠さない)
自分ができるマインドとしては、『自分がミスをしたかもしれない』と思うことです。先ほども述べたように、自分の過ちを認めることは難しいです。
ただ、もう2度と他の人にも同じ思いをして欲しくないと思えば、声を上げる勇気が出てくるのではないでしょうか?
本書では、航空業界が失敗から学ぶ姿勢を大事にしているのは、たくさんの命の犠牲の上に成り立っていることを忘れてはいけないと語っています。
ミスをしたことよりもミスした後に何をするかが大事ではないでしょうか?
質よりも量(成長に失敗はなくてはならない)

成果を出すためには、たくさんの失敗をしなくてはならないのです。最初から完璧なものを作ろうとしても上手くいきません。失敗の数だけ前進できると考えるべきです。
例えば、バスケットボール選手のマイケル・ジョーダンはたくさんのゴールを決めてきました。
しかし、記録によると最もシュートを外した選手でもあるのです。ウイニングシュートを任されて、26回も外しています。誰よりも失敗している選手と言えますね。
成果を出すには、たくさん試行錯誤を繰り返さなければ見えないこともあります。
失敗に対する捉え方や考え方が変われば挑戦回数が増えますね。
ひすいこうたろう 名言セラピーから失敗から立ち直る、活かす方法
事前検死(失敗したことを前提にこれから何をするか?)
今行っているプロジェクトが失敗したとします。その後に何をしますか?を失敗する前に考えることです。
何が原因で失敗したのかを仮説し、そうならないためにどうすればいいかをコミュニケーションをとりながら決めていきます。そうすることでプロジェクトをより良いものに出来ます。
要約・まとめ

- 正確なフィードバックがないと失敗から学習できない
- 成長マインドセットを持つ
- 失敗が起きたら人ではなく、方法やシステムに目を向ける
失敗から学習出来る組織と学習できない組織の違いについてまとめてきました。
自分で失敗を認めることが難しいと感じるのならば、歴史や他の人の失敗を記録することがいいです。航空業界や医療業界のたくさんの失敗事案が載っているので、気になる方は手に取ってみるのはいかがでしょうか?



コメント