もっといいチームにしていきたい。人間関係をもっとよくしていきたいと思うことはありませんか?
本書『問いかける技術』は組織心理学者の第一人者エドガー・H ・シャインが著者で地位が低い立場の人は上の立場に進言することは難しい。だから上の人間から尋ねることで問題を洗い出し、解決することが出来るということを教えてくれます。
とは言っても部下に何かを教えてもらうのは、管理職として職務放棄ではないか?と思ってしまうことがあるかもしれません。まさにこのような考え問題を潜在化させてしまう原因になっています。
仕事の考え方として、課題を遂行することが職場の信頼関係を築くことよりも優先になってしまっています。人間関係の方が大事というつもりはありません。
ただ、信頼関係を築くことに時間や努力を使えば、もっと問題解決がスムーズになるというのが著者が言いたいことです。
- 仕事でいろんな人の意見を聞くことで、アイディアがたくさん出る
- 仕事の人や家族と信頼関係を築く
- 自分に問いかけることで、もっと考えてから行動すればよかったと思うことを避けれる
問いかける技術とは?

自分の部下など下の人間に対して、相手の意見を求めるために質問することです。具体的には
- 「今ここで必要な謙虚さ」で質問する
- 興味や好奇心を持って尋ねる
問いかける技術で獲得したいことは、
- 必要な情報
- 相手との信頼関係
- 問題解決
などです。
「今ここで必要な謙虚さ」で質問する
今ここで必要な謙虚さとは、私は相手よりも一時的にも知らないことがある、助力して欲しいことがあるのを認めることです。なぜ、これが必要かというとお互いが依存関係にあるからです。
例えば、仕事で部下がミスをしてクライアントに迷惑をかけたら会社全体の損失になります。そうならないために、仕事の進捗を確認したり、見落としがないかを情報を共有することが大事です。
上司が部下に質問する時も同じです。自分が何かチームの輪を乱すことをしていないかを当事者に尋ねなければなりません。
しかし、部下は悪い振る舞いをしているあなたに何も言いません。それはリスクが高いと思っているからです。「あなたの傲慢な態度はチームの雰囲気を悪くしている」なんて言えませんよね。
ここで大事なのが今ここで必要な謙虚さです。
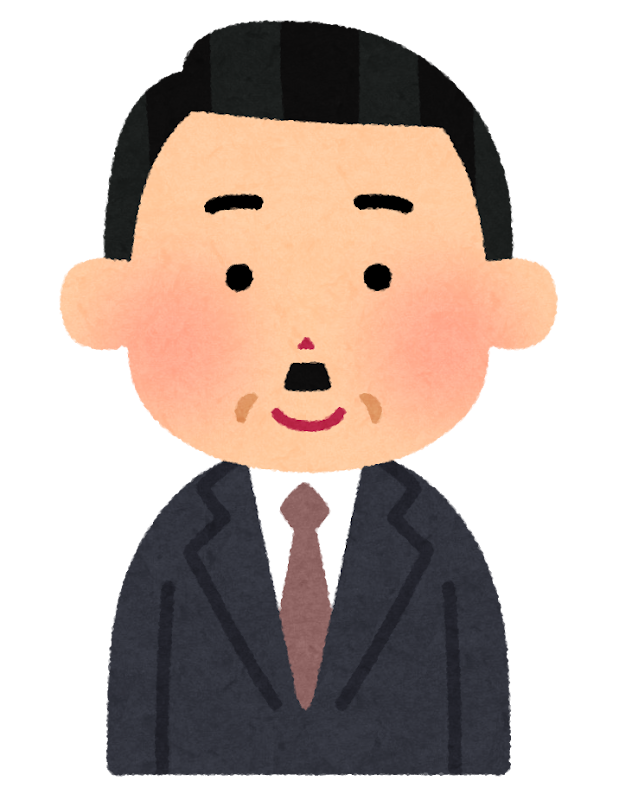
私は、〜(部下の名前)についてよく知らないのだ。君とはよく話をしているのを見るので、よかったら彼について教えてくれないだろうか?
自分は部下よりも知っていることが少ないので教えてほしいと言うことで、自分が必要な情報を獲得することが出来るのです。部下も自分の知っていることで、人の役に立てたと思うので充実感を得られることが出来るのです。
一つの質問から組織が活性化することもあるのです。
興味や好奇心を持って尋ねる
相手との信頼関係を築くには傾聴が必要です。傾聴とは、ひたすらに耳を傾けることではありません。興味や好奇心を持って問いかけることが大事です。
話を聞いてもらっている時、相槌だけしていると
「この人、私の話聞いていないな。」と思うことありますよね。相手が描いている頭の中の映像を共有できるために必要なことを質問するようにしましょう。
LISETENという本の中では、人の話を聞けないというのは、人生をつまらなくしているのと同じと言っています。自分の価値基準の中でしか生きていない人は、新しい発見や学びの機会を失っているのです。
私たちは、自分が話すことを優先してしまいます。それは、自分の有能さや正しさを相手に示したいと思っているからです。ただ、相手にはあなたは何も知らない無能というメッセージを送ってしまっています。
信頼関係を築くにはどうすればいいかというと、あなたの人間性や価値観に興味があるので聞かせて欲しいと好奇心を持って相手に尋ねることが大事です。
謙虚に問いかける技術を習得するには?

- 自分に問いかける
- マインドフルになる
- 相手の視点に立つ
自分に問いかける
何か行動する前に、自分の感情を言葉にすることから始めましょう。なぜ、自分に問いかけることが必要かと言うと、大きな失敗を回避するためです。
私たちが何であんなことしてしまったのか?と後悔してしまうのは、咄嗟の判断でちゃんと準備をせずにやってしまったことが多いです。しかも、今の感情によって判断が変わってしまうことがあります。
例えば、奥さんとケンカした後に出社した時、部下がミスを報告してくれたのに、いつもより辛く当たってしまったなどです。もっと別の言い方があったのではないだろうかと後悔します。そして、結果チームはうまく機能しません。
なので、自分は奥さんとケンカして気が立っている。だからいつもより周りの人たちに丁寧に接するようにしないといけない。と自分の感情に気づき、行動するときに気をつけることはないか問いかけます。
大事なのは、行動する前に自分に問いかけることです。そうすることで、客観的に自分を見ることで感情的な判断を避けることが出来るのです。
書評 メモの魔力 自己分析でやりたいことを見つけ実現させる方法
【書評】究極のマインドフルネスをまとめ・要約・感想〜悩みをなくす
【書評】はじめての「アンガーマネジメント」実践ブック・まとめ・要約
マインドフルになり、周りのことに気づけるようになる

私たちは、大抵のことを見過ごしてしまいます。ただ、内省していると、今まで見えていなかったことに気づけるようになります。
例えば、Dark horse〜好きなことで生きていく人が成功する時代という本の中で、好きなことを見つけるには、どんなことで自分は楽しくなるかという小さなモチベーションを知ることと言っています。
他には、自分に子どもができると自分の周りに妊婦や子どもが増えたように思えます。これを心理学ではカラーバス効果といいます。
つまり、自分が所属しているチームの人たちに何か困っている人はいないか?落ち込んでいる人はいないかなど、マインドフルに意識することで問いかけるための下準備ができるようになるのです。
相手の視点に立って行動し、自分で振り返る
仕事で地位が上がっていくほど、共感能力は下がってしまいます。理由は、部下の感情を気にし過ぎてしまうと、仕事の指示がしにくくなってしまうことがあるからです。
例えば、仕事で部下が出してくれた提案が会社の方針にそぐわなかった場合には、却下しなければならないです。しかし、それを相手のことを気にしすぎて受け入れたら苦しくなるのは自分です。
相手の立場になって物事を考えることが大事です。私たちは、自分と相手は同じ考えだと思ってしまいます。しかし、そのようなことはほとんどありません。むしろ、合っていたら奇跡と思った方がいいかもしれません。
私が相手だったらと想像することを習慣にすることで、共感能力が高められて相手と信頼関係を築くことが出来ます。
そして、行動した後にもっといい選択があったのだろうか?と振り返ることで後悔のない選択が出来るのです。
問いかける技術の感想→とても良書でした

本を読んでいると、傾聴や聞く力について書かれているのはよくあります。ただ問いかける技術の中で、組織で部下や同僚に接するときに、謙虚な姿勢が大事だということを書かれていた本はありませんでした。
私の実生活に取り入れようとしていることは
- 行動する前に自分に問いかける
- 自分の理解が曖昧なところ詳しい人に教えてもらう
- 周りをよく見て問いかける練習をする
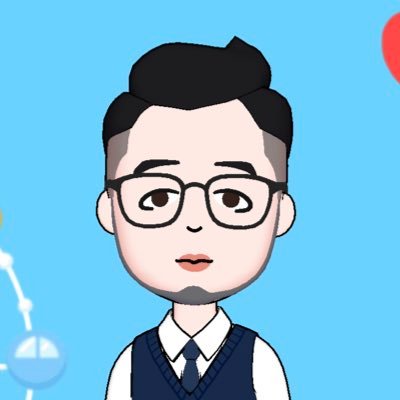
実践するにはどうすればいいか?とてもわかりやすい内容でした。
問いかける技術のまとめ

- 謙虚になるには、自分と相手が依存関係にあることを理解する
- 謙虚になるには、自分が相手よりも一時的にも知らないことがあることを認める
- 問いかける技術を鍛えるには、行動する前に自分に問いかける
仕事や家族にネガティブなフィードバックを受けることは気持ちいいことではありません。しかし、それを受け入れなければ、相手との信頼関係を築くことはできません。不意にくるフィードバックよりも自分から求めてきたものの方が「確かにそういうところがあったかもしれない。教えてくれてありがとう。」と前向きに捉えやすいのではないでしょうか?
そのために、組織心理学者の第一人者のエドガー・H ・シャインが書かれた『問いかける技術』手に取ってみるのはいかがでしょうか?
家族との信頼関係を築くには



コメント