頼み事は苦手だから自分でやってしまう。頼み事をするのは相手に悪いと思っている人はいませんか?
仕事を一人で抱え込んでしまうことで、時間を無駄にしている。頼んでおけば残業せずに帰れたのにと思うことはあるでしょう。
著者ハイディ・グラント氏『人に頼む技術』では
- 頼み事が難しいと感じているのはたくさんの勘違いが原因。
- 人に頼む方法は悪いやり方と良いやり方がある。
- 人を動かすには3つの力をうまく利用する事が大切。
が詳しく書かれています。仕事で自分の能力を発揮するには、全て自分でやってはいけません。自分ができる範囲を明確にして、周りをうまく生かす事が必要なのです。どうやっていいのか分からない方には、人に頼む技術は役に立てます。
この記事では、人に頼む技術の内容を要約し、まとめたものになります。
- 人に頼む技術の要約した内容
- なぜ頼み事が難しいと感じる原因
- 悪い頼み方と良い頼み方
- 人を動かす3つの力
なぜ頼み事は難しいのか?

社会的苦痛・脅威を同時に味わうかもしれない
頼み事をして断られたときに様々な苦痛を同時に受ける可能性があるのです。
頼み事によってもたらされる脅威は以下の通りです。
- ステータスの脅威→自分は周りにちゃんと評価されているか
- 確実性の脅威→未来を予測して対応したい欲求
- 自律性の脅威→自分ではどうしようもない事があるのではという疑念
- 関係性の脅威→仕事仲間や家族と良好な関係を築けていないのではという疑念
- 公平性の脅威→自分と周り公平に扱われていないのでは
この脅威を恐れて、頼み事を躊躇して自分でやってしまっているのです。
【書評】著者 根本裕幸〜執着を手放して幸せになる本を要約・まとめ・感想
【書評】究極のマインドフルネスをまとめ・要約・感想〜悩みをなくす
断られる可能性を2倍高く見積もる
私たちは、相手に頼むときに相手の立場になって考えることを忘れてしまいます。それは、相手が断るときの精神的負荷です。自分が頼まれごとをされたときに断りにくいなと思うことはあるでしょう。
しかし、自分が頼む側になった時にはそんな面倒だからやりたくないと自分のことを気遣わずに断るのではないかと疑ってしまいます。
予測していた断られる確率と実際に断られる確率は2倍も差がありました。さらに、一度断られたら次に別のお願いをしても無駄だという思い込みもあります。
断る立場の人からすると、同じ相手に2度断るのは自分は嫌なやつだとセルフイメージを下げてしまうのです。
なので、頼み事は一回断られてももう一度お願いしたら2回目の方が引き受けてくれる可能性が高まるのです。
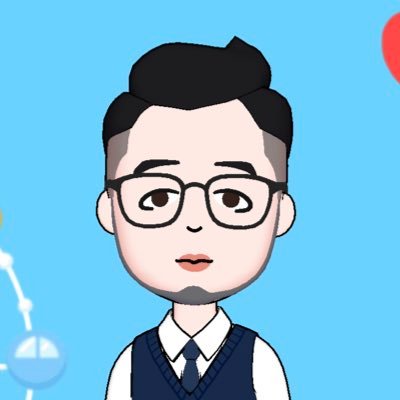
もし、断られたら何でダメなんですか?と聞くと7割は引き受けてくれます。断った時に何となく断ってしまうこともあるんですよね。
頼み事をすると嫌われるという誤解
人を助けるという行為にはメリットがたくさんあります
- 助けることは気分を高める
- 罪悪感を緩和してくれる
- 人生の満足感を高めてくれる
人間は集団をなす生き物です。なので、自分が落ち込んでいたり、気分が下がっている時ほど、周りの人助けようという欲求が働くのです。
また、幸せをお金で買う5つの授業の中でも他者に投資することは幸せに直結すると言っています。自分が社会のために役立っているというセルフイメージの向上を促しているのです。
このようにメリットがあることを頼む人は知ってはいると思います。
ただ、自分が頼む時には、前述の社会的苦痛の方を強く感じてしまい、頼むことを躊躇ってしまうのではないでしょうか。
悪い頼み方と良い頼み方

- 自律性(コントロールされていると思うとやる気がなくなる)
- 返報性(お返しをしなければという心理)
- 内発的動機付け(自分が行動しようとする心理)
相手も助けるし、自分も助ける持ちつ持たれつな関係を築く事が大切です。
悪い頼み方
- 共感に頼りすぎる(私はとても辛い思いをしています。だから助けてください。)→相手は辛すぎると背負いたくないと思ってしまう。心理的負荷が大きくなってしまう。
- やたらと謝る→よそよそしい対応。仲間意識を築きにくくなる。相手が喜んで次も助けたいと思えなくなる。
- 言い訳をする→頼み事をするのが悪いことの様に思ってしまう。相手も頼みにくくなる。
- 頼み事をやると楽しいことをアピール→楽しいかどうかは相手が決めること
- 助けられた時の自分のメリットを言う→自分のメリットよりも相手の人間性を褒めた方がいい。例えば、あなたは頼りがいがあって人に手を差し伸べるところをすごく尊敬します。
良い頼み方
STEP1助けて欲しい時に相手に気づいてもらう
私たちが思っているほど相手は周りのこと見ていません。自分のことで手一杯です。それをまずは認識することです。人は周りに注意を向ける事が難しい原因がいくつかあります。
- 目の前のことに集中していると、周りのことに気づかず不注意による見落としが起きやすい。
- 助けようとしている側がネガティブな感情になっていると、周囲の状況に気付きにくくなる。
- 目に入る情報が多すぎると助けるべき人に気づけない
何で助けてくれないのだろう?と期待してもしょうがないのですね。助けてもらうためには、相手に助けが必要と伝えなければならないのです。
STEP2相手に助けていいと確信を持ってもらう
相手は、自分が本当に助けて良いのかと尻込みしています。その理由は
- 助けが必要だと誤解してしまう。
- 求められていないのに助けようとして嫌われてしまう不安。
- 助けようとして断られ、恥をかいてしまうかもというリスク。
助ける側になってみると、このような心理的な負荷があることが分かります。ただ、頼む側になってみると気づけないことも多いのではないでしょうか?
やはり、私は助けが必要であることを相手に伝えなければなりません。
STEP3自分が助けなければと責任を持ってもらう
助けようか判断している時、周囲の状況を確認します。そして、他の人が助ければ良いだろうと思うと人は助けてくれません。
なので、あなたじゃないとダメなのです。という風にお願いをすることで相手の自尊心を刺激します。
人間は正しい人間であり続けたい欲求を持っています。助けを求められているのならそれに応えたい。そういう人間でいたいといったように。
そこで、相手に自分がやるべきと自発的に行動してもらうことで、相手の幸福度も高くなってウインウインの関係になれるのです。
STEP4相手が助けられる状況か確認する
相手が自分のことで手一杯の時には負担になってしまいます。なので今はそれなりに余裕があるように見える時に頼むことで成功率を上げる事ができます。
そんなこと言っても、余裕がある時なんて基本的にはないのではないのかと思うかもしれません。
そこで、忙しい相手にも助けてもらうためには3つのことを意識します。
- 具体的に何をどのように助けて欲しいのかを伝える。
- 妥当な量の援助をしてもらう(多くなりすぎないように)
- 相手のやり方を受け入れる(自分が望んだ形ではなくても)
援助は、助ける側のコントロール出来ることを多く残しておく事が肝心です。当たり前かもしれませんが、時間を使って助けてくれているので出来るだけ相手を尊重する心構えが必要なのです。
人を動かす3つの力

仲間意識を持たせる
頼む時に『一緒に』を使う
相手に自分の仲間であることを認識してもらわなければ相手は、助けようとしません。所属欲求を刺激する言葉が一緒にです。
例えば、自分が与えられた仕事が納期に間に合わなそうだった時に、他の人にフォローしてもらわなければならないとします。
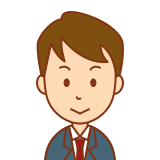
この資料が期日までに間に合わなさそうです。〜さんのお時間の都合がよろしければ一緒に一部を作っていただけませんか?
自分の仲間が困っていることを改めて「一緒に」という言葉を耳にすることで認識します。
人を動かすには人間の根源的欲求を刺激する事が大事なのです。
『本要約』モチベーション革命 感想 世代における価値観の違い
本 要約 佐渡島庸平(コルク代表)コミュニティに入らないと孤独
共通の目標に向かっていることを認識させる
チームがうまく機能していない原因の一つにチームの目標が共有されていない事です。理由は、どのように行動すれば良いのかが分からなくなってしまうからです。
逆に、目標が明確化されていると、行動がはっきりするし、困っている人がいたら自分たちの目標の支障が出ることを敏感に察知するのです。
共通の目標は、人を動かす大きな原動力になるのですね。
客観的共通点ではなく、経験や感情を共有する
相手と仲良くなりたいなら共通点を探すとよく聞きますよね。
しかし、それよりも人間は経験や感情を共有することの方がより親密度が増します。
例えば、相手と同じ出身地だったします。それで仲間意識が強く刺激されることはありません。なぜならその出身地全ての人を仲間と思うにはカテゴリーが広すぎるからです。
次に、都会に上京してきたという共通点があったとします。人の歩くスピードが早すぎてびっくりしたという体験を共有することで感情が動きます。
感情が結びつくことで、親密度が上がりこの人のためならと仲間意識で行動するようになるのです。
【書評】知性豊かで創造力がある人になれるLISTENを要約・まとめ
自尊心を刺激する

「あなたは親切な人」ラベリングで伝える
子供に整理整頓をさせたいときに、「あなたは、お片付けをしないとダメですよ。」というよりも「あなたは、お片付けができる親切な人。」と言うのでは、後者の方が効果が高かったのです。
何でも〜な人とつけてお願いすれば良いかというとそうではありません。相手が言われて自尊心が高まることでなければいけませんよね。自分が言われて嬉しい事が相手もそうだとは限らないからです。
それを知るにはどうすれば良いかというと、観察することです。この人はこの話をするときに嬉しそうな顔すると仮説を立てます。
それをひたすら試すことで、相手が喜ぶツボを見つける事ができるのではないでしょうか。
感謝をしないと次に助けてくれる可能性が半減
良かれと思ってやった行動をしても相手に感謝してもらえないことで、不快になった経験はないでしょうか?恋人やパートナーに感謝を言ってもらえずに気落ちした経験は誰でもあると思います。
相手も同じです。言ってもらえなかったことが引っかかっていて助けた方がいいのに見送ってしまう事が増えてしまいます。
そればかりか、頼み事をしても断られてしまう可能性が2倍になってしまいます。頼み事は助けた側、頼む側の両方にメリットがあるのにそれを物にできなくなってしまうのです。
また、感謝は言われる側だけでなく、伝える側にもメリットがあります。それは、自分は周りの多くの人に支えられている。生かされているという実感を抱くことで幸福度が上がります。
自分も相手も幸せにしてくれる感謝。やらないのは人生を損しているとしか言えないですよね。
あなたにしか頼めない(責任の分散を回避)
誰でも出来ることで貢献しても自尊心は高まりません。自分にしか頼めないことであることを伝えることで、相手の自尊心を刺激する事ができます。
なので、相手が何が得意なのかを普段から観察しておく事が大切です。この頼み事は誰にすればいいのか分からなくなってしまうと、考えるのが面倒になって結局自分でやってしまいます。
頼み事は技術です。やらなければ身につきません。どういうことを誰に頼むかを明確にすることで迷いなく行動する事ができるのではないでしょうか。
有効性を示す

助けてもらえることで、どのような効果があるのかを伝える
自分が助けたことで、相手やチームにどんな影響があるのかを明確にしたいのです。逆に、やってもやらなくてもいい仕事で充足感が満たされることはありません。
- なぜ助けて欲しいのか?
- あなたのこの能力でチームにこんな影響がある事が見込める
- あなたの力でより良いものに出来る
などを伝えることで、自分の能力をチームに貢献出来ているという自己効力感を刺激する事ができるのです。
どのような効果があったのかを伝えることを事前に説明する
頼み事を引き受けてもらってその後に何も伝えないのは、相手に失礼です。どんな影響があったのか?自分は力になれたのかを知りたいのです。
例えば、コカ・コーラの社長を16年間勤めたロベルト・ゴイズエタ氏は大株主のウォーレン・バフェットに毎日電話をしていたのです。
自分のところに多くの出資をしてくれているウォーレン・バフェット氏に「ペプシは次にこんな戦略を打ってきました。」「これから、会社をこのように運営していこうと思います。」など伝える事で誠意を見せていたのではないでしょうか。
相手にどのような効果があったのかを伝える事で、次何か困った事があった時も助けようとしてくれるのです。
相手のやり方を優先する
自分のやりたいことややり方を優先するのではなく、相手に決めてもらうのです。なぜなら自律性を伴わない頼み事はメリットが少なくなってしまうからです。
私たちは、やり方をがんじがらめに決められてしまうと、モチベーションが低下してしまいます。自分で決められるだけの余白がないと、いいパフォーマンスが発揮出来ないのです。
やってもらうのは、相手なので相手が困らない量や都合をしっかりと加味した上で頼むようにしましょう。
人に頼む技術〜要約・まとめ

- 頼み事をするには、苦痛を伴い、断られる可能性を高く見積もり、助けるメリットに目をつむる
- 正しい頼み方は、相手に気づいてもらい、自律性を促し、相手の状況を確認する人を動かす
- 3つの力仲間意識、自尊心を刺激、有効性を示す
頼み事をするのに、すごく嫌な感情を伴うので、自分でやってしまっている人は多いと思います。
人に頼む技術を読むことで、仕事を早く終わらせいい人間関係を築く手助けができます。
気になる方はぜひ手に取ってみるのはいかがでしょうか?



コメント